いよいよ、新築マンションへの引っ越しが近づいてきました。
子育てしながらの引っ越し準備は、なるべく早めから取り掛かりましたが、どんなに頑張っても達成率は80~85%で高止まりです。
生活しながらの準備は大変ですね。
引っ越し前後はバタバタしがちなので、引越し前後にやっておかなければならない手続き関係を、まとめておこうと思います。
あくまで我が家の場合なので、同じ状況や家族構成の方に参考にしていただけると嬉しいです。
【引越し前】賃貸管理会社への連絡
我が家は、会社の借り上げアパートで、賃貸契約は会社なので、引越しに際し、引き渡しの立ち合い等は必要ありません。
確認したら、鍵を閉めてドアポストに投函しておけばOKだそう。
立ち合いが無いだけで、引越し荷物を出してすぐに引っ越しトラックを追いかけられるので、とっても楽です。
以前は、引越し荷物を出した後に、立ち合いの予約を取っていました。
予約時間がすぐ後ならいいですが、引越し繁忙期と重なると、引越し当日に立ち合いが出来ない場合や、時間が後ろにズレる可能性もあるので、管理会社への引越しの連絡はなるべく早い方がいいですね。
水道・ガス・電気の利用停止・開始手続き
我が家は、引越し後も主人が(ほぼ何もない部屋で)主人が生活するので、各種手続きは主人が完全に部屋を引き払う日を基準に手続きを進めました。
使用料のお知らせ等に記載されている「お客様番号」があれば、簡単にインターネットから申し込めるものもありました。今回は電気料金。
ガスは、立ち合いでの閉栓の手続きが必要なので、年度末時期は早めに連絡をしておいた方がいいでしょう。
人手が足りなくて、手続きが出来ないなんてことになったら大変です。
引越し日が決まったら、すぐに連絡をすることをお勧めします。
我が家は1か月前にすべての手続きの連絡をしました。
クレジットカード払いや口座振替にしていて、料金の精算が無ければ、停止の連絡をするだけで大丈夫です。
後日、料金のお知らせや引き落とし明細を新住所に郵送してくれます。
引越し先においても、利用開始の手続きが必要です。
ガスは立ち合いが必要なので、事前連絡必須です。
水道・電気の場合、電話連絡やインターネット手続き等で対応可能な場合があるので、利用停止の際に確認しておくといいでしょう。
電気の場合は、市外への引越しでも、同じ電力会社であれば、スムーズに利用開始手続きが行えます。
住民異動届(転居届・転入届)
引っ越し前の住所の役所に行って住民異動届(転出届)を提出し、転出証明書を貰ってきます。
その後、引っ越し先の近くの役所に行って、住民異動届(転入届)を提出します。
転入届を提出する際に、前の住所を証明するための転出証明書が必要になるので、忘れずに持参しましょう。
住民票を移すのに必要なものは、①印鑑(要らない所も多い)、②顔写真付きの本人確認書類(免許証、パスポートなど)の2点だけです。
印鑑は必要ない所も多いので、事前にインターネット等で確認しておくか、印鑑も100円ショップのものでいいので、役所の手続き関係は持って行くといいと思います。
今回は、私と息子だけの引越しですが、便宜上、世帯全員の住民票の異動を行う予定です。
住民票の異動時期は、主人の職場から支給される、転勤費(引越し代金に相当するもの)に関係してくるので、事前に総務部に確認をして、3月の初めに引越しをしても大丈夫かどうか確認しました。
今回は、県外からの引越しだったので大丈夫でしたが、県内での転勤による引越しの場合、転勤の辞令前に引越し(住民票の移動)をしてしまうと、引越し代が出ない可能性もあったそうです。
会社都合の引越しなのに、引越し時期で引越し代が出ないかもしれないなんて、絶対に嫌ですから、事前確認(メールで証拠保管)は重要ですから。
市内の引越しで、立ち合いの為だけに前の住居へ出向くのが楽な人は、立ち合いは別の日にした方が楽かもしれません。
住所変更手続き(印鑑登録・こども医療費助成等)
印鑑登録の引越し手続き
実印の印鑑登録は、不動産取引、住宅ローン契約、自動車登録など引越し後も、大切な手続きや契約などで必要になります。
今回は、住宅ローン関係で必要になると思います。
住民票の異動の際に、引越し前後の役所で「印鑑登録の廃止&再登録手続き」も合わせて行うことにします。
これは忘れてそうだったので、事前に調べておいてよかったです。
国民健康保険・国民年金等
国民健康保険に加入している場合、住民票の変更手続きが必要です。
異なる市・区間で引越しする場合、旧居の役所に「国民健康保険証」と「マイナンバーカードもしくは通知カード」を持参して、国民健康保険を脱退する資格喪失手続きを行い、新居の役所に「転出証明証」を持参して、加入する手続きが必要です。
私は、主人の扶養家族になっているので、社会保険に加入しているので、健康保険や年金等の役所での手続きは必要ありません。
主人が、職場に住所変更届を提出すればOKです。
ちなみに、国民年金の引越し手続きは、住民票の異動手続きと合わせて住所変更されるそうで、原則、引越し時の手続きは必要ありません。
児童手当
引越し先が引越し前と違う市区町村の場合
- 引越し前:①児童手当給資格消滅届を提出(15日前~引越し当日)
- 引越し後:②児童手当認定請求書を提出(15日以内)
が必要となります。同じ市区町村の場合は①は必要ありません。
児童手当給資格消滅届提出の際、所得課税証明書もしくは住民税課税(非課税)証明書を発行してもらうといいそうです。
これらの証明書は、新住所での②児童手当認定請求書を提出する際に、必要になるかもしれません。
請求者と配偶者の所得状況を役所が確認出来ない場合に、請求者と配偶者の「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要になるそうです。
もし必要になった場合に、転居前の市区町村で発行してもらう必要があるので、遠い場合は郵送による請求等、手続きが面倒になります。
必要ない場合もあるので、事前に新住所の役所に確認しておくのがいいでしょう。
こども医療費助成
こども医療費助成は、市区町村により呼び方や助成期間は異なりますが、子供が医療機関で診療を受けた際、医療費の自己負担分を助成してくれる制度です。
こどもが小さい頃はよく病気するので、医療費助成はとても助かる制度ですよね。
我が子は、引保育園にも行っていないので、病気をすることはほとんどありませんが、1年に1,2回は風邪をくので、その際はお世話になっております。
幼稚園に通うようになったら、病院を受診する機会が増えると思われるので、こども医療費助成の手続きは忘れずにしておかなければいけません。
手続きは、引越しから1か月以内に行うと、引越し当日から受給資格が得られるので、手続き前であっても遡って助成してもらえます。
引越しによる環境の変化で体調を崩すかもしれないので、病院を受診するのを躊躇しないためにも、手続きは忘れずに。
妊産婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受験票
妊娠中に異なる市・区に引越しする場合、役所で手続きが必要です。
手続きには、旧居の役所で交付された「母子手帳」と未使用分の「妊婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受検票」が必要です。
母子手帳は交換の必要はなく、そのまま使用できます。
確認事項があるかもしれないので、手続きの際は持参するといいでしょう。
各種受診票を交換し、引越し先の市・区で受けられる出産・子育て支援サービスの配布物を受け取ります。
出産病院も変更する場合、転院のための妊婦健診が必要なため、受診票の枚数が足りなくなるかもしれません。
診察内容と金額によって、受診票を使用するかどうか病院窓口で相談するといいでしょう。
まとめ
今回、自分のメモ程度ですが、引越し前後で必要な手続きについて記事にしました。
息子は未就学児なので、学校に通っているお子さんがいる方は、転校に必要な手続きも出てくると思います。
夫婦二人だけで引越しを繰り返していた頃は、
銀行口座などの住所変更手続きが面倒だなぁって思っていましたが、
子供が出来ると忘れてはいけない手続きがいろいろあって、
そういった手続きがさらに面倒に感じました。
マンションを購入して、もう引越しをすることは無いと思うと、あと1回だけだし、頑張ろうと思います。

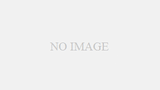
コメント